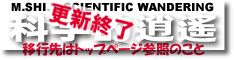引越しやら何やらで、書き忘れてました……本は読んでいたのですけどね。
- ■ リチャード・フォーティ著、渡辺政隆訳『生命40億年全史』(草思社)
-
面白かった。
とくに、カンブリア爆発以前の単細胞生物の時代について、手を抜かずに、生き生きと描いている点で、他の生物史の本とは一線を画します。
ただし、高校生物履修済み程度の能力を読者に要求します。
もっと(基礎的な)図版を追加したり、生物の体制(基本的な体構造)や発生の過程をコラムにして載せたりすると、もっと多くの読者層にウケるのでは、と思いました。
読んでいる最中、面白いなぁと思ったところをいくつか、引用します。
まず、古生物学者はタフでなければならない、という話(太字は私が追加しました。以下同様)。 - つぎに、やっぱり出たかマーフィーの法則。
- 進化についての考え方として、きわめて重要なポイント。 ホント、「生物の設計者」を仮定するのは生命に対する冒涜だと思いますよ。
- チャールズ・ダーウィンの自宅、ダウンハウスにて。
- 天体衝突による恐竜絶滅仮説の「証拠」となったイリジウムの層が見つかる「K・T境界」を見に、イタリアのグッピオへ出かけると……。
- 研究者についてのエピソードもいろいろあります。
- 次の話に似たことは、前にクイズにしたことがあります。
- ……ということで、イギリス流のユーモアが絶妙の味付けになっているのかも知れませんね。(2003/07/いつだっけ……読了)
直径数千分の一ミリの微化石を求めて一万平方キロメートルにもおよぶ先カンブリア時代の地層に立ち向かう古生物学者の執念にも似たがんばりを支えるのは、また別の種類の忍耐強さである。ビル・ショップ教授は、その種の化石ハンティングに関してもっとも経験豊かな人物の一人で、疲れを知らなかった。彼が一年間の有給研究休暇をロンドンの大英自然史博物館で過ごしているあいだ、私がオフィスを閉めたあとも、彼の部屋だけ毎晩遅くまでこうこうと明かりがついていた。ぜったいにめざすものを見つけるという決意で、彼は連日、何百枚というスライドを顕微鏡でのぞいていた。退屈で放り出したくなるような仕事だ。地層のどのあたりのどんな種類のチャートを探せばよいかという見きわめが徐々につくようになるので、発見に要する時間は短縮されてはゆく。それでも、何より辛抱強さの要求される仕事である。古生物学では、さまざまな場面でこの種の忍耐が必要とされる。飽くことを知らない探求と無謀な探求を分ける一線は、ときとして微妙だ。しかし、たとえ失敗に終わった調査でも、あとに続く者たちにはほかの場所を探せという助言にはなる。偏執的な執念は、おそらく最後には役に立つのだ。(第2章 塵から生命へ p.92〜93)
三葉虫の化石を含んでいる太古の岩石が見つかるのは、先カンブリア時代の大陸の辺縁部にあたる場所であり、そこにたくしこまれて辺鄙な土地に埋もれているか、人けのない海岸沿いに横たわっているかである。しかも、最高の標本はいつもベースキャンプから一番遠い場所で見つかるという法則は、すでに何度も実証されている。(第5章 豊穣の海 p.183)
私は木の進化を説明するにあたって、あたかも工学的な設計原理が考慮されたかのような書き方をしたが、そのことについて弁解するつもりはない。なにしろ、いずれもまさに驚嘆すべき構造なのだ。初期の植物に起こった一連の変化を、「改良」という言葉を使わずに記述するのは不可能だと言ってもいい。ただしそれは、母なる自然の導きがあったとか、何らかの超自然的な力がはたらいたというように、設計者の存在を認めることと同義ではない。設計原理が設定されたのは、気孔をそなえた葉が進化すると同時に、光をめぐる競争が生じたことの論理的帰結とでも言うべきことだからである。樹木の形態のみごとさが、自然の設計のみによるものだという見方がつまらないと思うのは、それは、生物が進化の過程で何度となく発揮してきた創造性に当然払われるべき驚嘆の念を、過小評価しているからにほかならない。(第7章 森の静謐、海の賑わい p.254)
ダーウィンの研究がいかに自宅周辺で行なわれたかは、そこを訪問してみてはじめて実感できることだ。(中略)重要なミミズの研究を行なったのも、屋敷の敷地内だった。彼が重要な結論を引き出すもととなった対象は、恐竜などではなくフィンチ類という、決して派手ではない鳥だった。種の起源に関するダーウィンの考察は、自然界の見方を一変させ、小説にとっての文法と同じくらい、私がここで語っている物語を支えている。ダーウィンの大統一理論は、壮大な現象も控えめな現象も等しく支配してしまったのだ。(第9章 壮大なものと控えめなもの p.352〜354)
やがて、道の両脇は石灰岩の崖となり、急斜面には落石防止用のネットが張られている(むしろ落石によって化石が露出することを歓迎する地質学者には不評のネットである)。(第10章 終末理論 p.361)
哺乳類学者は、たった一個の歯からでも、その動物の種類をこまかく同定できる。氷河時代の哺乳類を専門とするわが同僚アンドリュー・カーラントは、北極圏に生息するとても重要なハタネズミ類の小さな歯をうっかり飲み込んでしまうという不運に見舞われたことがある。そんなものを口に入れていったい何をしていたのか、彼は語ろうとしない。推察するに、どうやらその歯に付着していた古い接着剤か何かをとろうとしていたようだ。結果的に彼は、何時間か待ってその歯を回収することができたのだが、これほど、哺乳類学者が歯の形質にいかに重大な価値をおいているかを雄弁に物語る落とし話はない。(第11章 乳飲み子の成功 p.393)
朽ち木の山や糞の山、洞窟の暗がりなどで、甲虫類の種類がどんどん増えていった。それがどのようにして進行したかはよくわかっていないが、甲虫類(鞘翅(しょうし)目)がおさめた成功のすごさは一目瞭然である。現生する甲虫類は、すべて名前をつけることはおろか、その全容さえ不明なほどの種数を抱えている。神の特質がよくあらわれていることは何かと問われた進化学者のJ・B・S・ホールデンが、「甲虫に対する途方もない肩入れ」と答えたという話は有名である。(第11章 乳飲み子の成功 p.421)